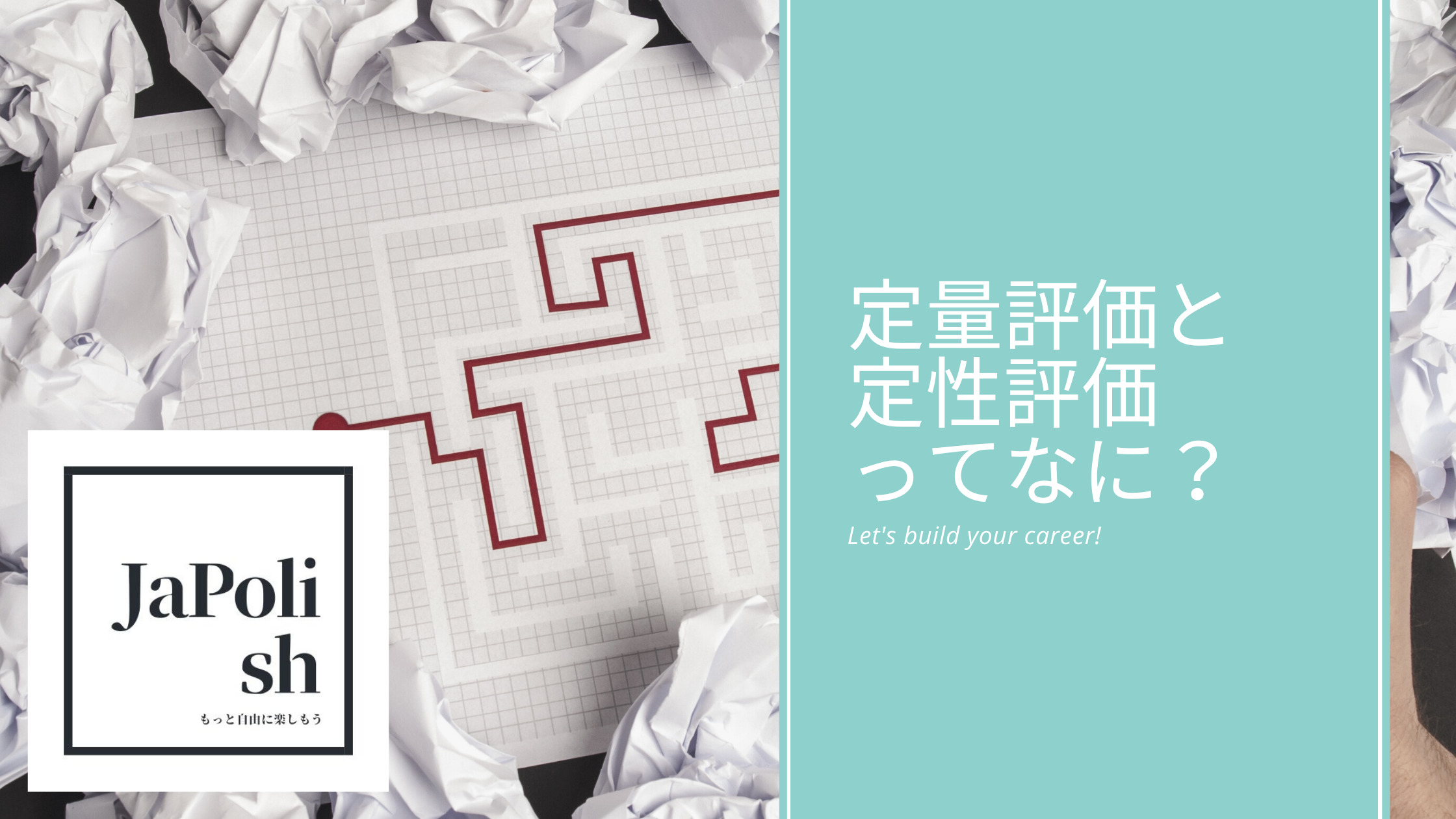こんにちは、ぼしおです!JaPolishの運営と記事執筆を担当しています。
今回は、人事評価制度でよく使われる「定量評価」「定性評価」という評価方法に関してご紹介します。会社は従業員の何を評価しているのか、良い評価を得るためにはどう目標設定をしたら良いのか、具体例とともに学んでいきましょう!
評価制度を理解した上で、目標設定を行うことが、正しい評価を得るためのファーストステップです!

正しい評価を勝ち取るためには、自分で用意!
- 定量評価と定性評価の違い・特徴
- SMART目標設定の方法
- 定量評価と定性評価への対策と準備
定量評価と定性評価ってなに?
「定量評価」や「定性評価」という言葉が聞きなれない方もいるかと思いますが、違いを理解すれば簡単なのでご安心ください。文字通り、「量」で測る評価と「性(質)」で測る評価のことです。
定量評価とは?
数値で計測できる指標を元にした評価です。例えば、「売り上げ目標を何%達成できたか」は数値で結果を示せるため、定量評価です。同様に「クレームの対応件数」や「新規案件受注数」なども、数値で結果を示せるものは全て定量評価の対象と言えます。
「定量評価は量だから、数値で示せる結果の評価」と覚えておきましょう。
定性評価とは?
数値では表すことのできないものに対する評価です。例えば、「リーダーシップを発揮できたか」は被評価者の素質を評価するため、定性評価です。同様に「責任感があるか」や「チームワークを大切にしているか」なども、性格や素質を評価するため定性評価と言えます。
「定性評価は性だから、性質や素質を測る評価」と覚えておきましょう。

漢字の意味と紐づけると、覚えやすい!
- 定量評価とは、数値で計測できる指標を元にした評価
- 定性評価とは、数値では表すことのできないものに対する評価
定量評価と定性評価の具体例・メリット・デメリット
定量評価と定性評価の違いがわかると、それぞれの良し悪しがなんとなく想像つくかと思います。人間が行うことなので、完全無欠で公正な評価方法というものは存在しませんが、評価方法の特徴を正しく理解して準備することは可能です!
ここでやってしまいがちなのが、被評価者=自分の視点だけで考えてしまうことです。人事評価というのは、評価をする評価者、評価をされる被評価者、評価制度を整えて運用している人事部、そしてそもそも私たちを雇用している経営者がいます。会社そのものと置き換えていただいても構いません。
それぞれの立場から「自分は何を期待されているのか」を理解し、その期待を満たすことで正しく評価を得られるように努めましょう!
被評価者にとってのメリット・デメリット
| 具体例 | メリット | デメリット | |
| 定量評価 | 目標管理制度が代表的 ・売り上げ目標達成率を評価する ・プロジェクト進捗率を評価する ・採用目標人数の達成率を評価する | ・数値で結果が示されるため受け入れやすい ・目標が明確であればモチベーション向上に繋がる | ・結果の責任者が自身でない場合においても、結果で評価される |
| 定性評価 | コンピテンシー制度が代表的 ・リーダーシップを発揮した取り組みを評価する ・責任感ある行動を評価する ・チームとのコミュニケーションを評価する | ・自身の言動や姿勢を評価してもらえる ・自身の成長機会に気づける | ・明確な基準ではないため、自己評価との差を受け入れづらい ・評価者との関係性に、評価が左右される可能性がある |
評価者にとってのメリット・デメリット
| 具体例 | メリット | デメリット | |
| 定量評価 | 目標管理制度が代表的 ・売り上げ目標達成率を評価する ・プロジェクト進捗率を評価する ・採用目標人数の達成率を評価する | ・結果が明確で評価がしやすい ・定期的な進捗確認が容易 | ・従業員が結果にのみ注力するようになる可能性がある |
| 定性評価 | コンピテンシー制度が代表的 ・リーダーシップを発揮した取り組みを評価する ・責任感ある行動を評価する ・チームとのコミュニケーションを評価する | ・会社組織が求める人材像に基づいて、人材育成が行える ・将来性や素質を評価できる | ・結果を出せない従業員でも、高く評価してしまう可能性がある ・被評価者との関係性に、評価が左右される可能性がある ・被評価者に納得してもらえない可能性がある |

視点を分けて整理してみると、どんな対策ができそうか見えてくるよ。
被評価者ができる定量評価への対策と準備
上述で整理した通り、評価をする側とされる側でメリット・デメリットに違いがありましたね。それはそっくりそのまま、期待値が違うと言い換えることができます。評価者が期待する成果を出せるように、できる対策ポイントを押さえておきましょう。
STEP1 明確な目標設定を行う!

何事も結果が全てや!!!数字を出せ、数字を!!!
と言うのは簡単ですが、まずはその数字の良し悪しを測る目標設定ができていないといけません。評価というのは、評価される時だけではなく、目標を立てるところから始まっているのです!まずは、目標設定の例を見てみましょう。
- A案:新人なのでまずは頑張ってたくさんの新規案件を取ってくる
- B案:2021年上半期中に500万円の売上げ目標を達成する
どちらが良い目標設定でしょうか?もちろんB案だと思いますよね。
では、どうしてB案の目標設定の方が良いのか、説明できるでしょうか?この良い目標設定をするための方法の一つがSMART目標設定です。
SMART目標設定
SMART目標設定というのは、目標を明確にするために重要な5つのポイントの頭文字をとったものです。
- Specific(具体的に):具体的な表現で書かれている
- Measurable(測定可能な):達成率を測ることができる
- Achievable(達成可能な):現実的に達成可能であると同時に挑戦的である
- Related(経営目標に関連した):会社や部署の目標実現に寄与するものである
- Time-bound(時間制約がある):期日が設けられている
これらを満たした目標設定をすることで、何に取り組むべきなのかより明確にすることができます。また、実際に査定が行われるタイミングで「目標の理解が違った。」というトラブルを防ぐことができます。
STEP2 現実的なアクションプランをたて、合意を得る!
目標が設定できたら、次はアクションプランです。「目標設定してたけど、他のことで忙しくて取り組めなかった。結果が出なくて評価されないなんてフェアじゃない!」なんて言い訳は通用しません。自分の目標達成のために、準備をして取り組むのは自己責任です。
- SMART目標:2021年上半期中に500万円の売上げ目標を達成する
- アクションプラン:全既存顧客に対して拡張プランの提案をQ1中に行い、20%の売り上げUPを獲得する。並行して、毎月10件の新規アポを行い、新規顧客獲得による売り上げUPを目指す。
評価者である上司とここまでの内容を合意していれば、あとはタイムラインをひいて毎日のタスクに落とし込む作業です。ここで、SMART目標のAchievable(達成可能な)の根拠となるよう、どのアクションでどれだけの成果をあげれば実現できるのかを測ります。「実際計算してみたら、全然届かない数字でした。」とならないように、戦略を立てて目標に取り組みましょう!
STEP3 進捗管理と軌道修正!

あとはあの手この手で取り組むのみ!!
目標達成に向けて、アクションプランの計画に沿って日々業務に取り組むわけですが、必ず定期的な進捗管理と軌道修正が必要になります。ここからは本当にケースバイケースですが、目標達成できるように頑張って取り組みましょう!
評価者である上司の方とは、定期的に進捗共有の時間を持つと良いかもしれませんね。他の業務で遅れが生じているようであれば、手助けしてもらえるかもしれませんよ。
- STEP1 明確な目標設定を行う!
- STEP2 現実的なアクションプランをたて、合意を得る!
- STEP3 進捗管理と軌道修正!
被評価者ができる定性評価への対策と準備
定性評価は定量評価とは違い、明確に数字で結果が出ません。期待される内容も、概念であったり、考え方であったり、人によって理解に差が生じてしまう評価方法です。そのため、定性評価も事前の対策ポイントを押さえてしっかり準備しておきましょう!
STEP1 定性評価の期待値を理解する!
定性評価を取り入れている多くの企業は、企業理念や企業が理想とする行動特性などを評価対象にしています。リーダーシップや責任感、チームワークなどですね。これは企業によって異なるため、まずは何が評価対象になるのか確認しましょう。
そして、評価者である上司に何を期待しているか聞いてみてください。

私のポジションで次のステップに進むためには、具体的にどのようなリーダーシップを期待されているかアドバイスいただけますか?現時点で、改善点などお気付きのことがあれば、ぜひ教えてください!
できる限り、評価者である上司の期待値を理解し、それを一旦持ち帰ります。そこから期間中に何ができそうか整理をして、目標設定してしまうのです。
STEP2 目標設定をし、合意を得る!
評価者である上司の期待値を元に、何に取り組むのかを明確にして上司に提示します。定性評価は数字で測れない評価であるからこそ、目標を設定して取り組むことが効果的です。
ほとんどの方が会社で指導されない限り、定性評価に対して目標設定をしないのですが、それは損をしています。自主的に目標設定をし、評価者と合意を得て、それを成し遂げたかどうかで評価をしてもらうことで、より自分に優位に査定を進めることができるのです。
STEP3 査定時の自己評価で優位にアピール!
- Aさん:リーダーシップを発揮して、チームに毎日声かけをして雰囲気づくりを頑張りました。チームのみんなと信頼関係を築くことができ、チーム全体のレベルアップに貢献しました。
- Bさん:〇〇さん(上司)とチームの課題について話し合い、兼ねてから課題認識のあった業務のスタンダード化に取り組み、マニュアルの作成とチームへのトレーニングを主導しました。
Aさんは特に何も用意をせず、査定のタイミングで自己評価を考えたパターンです。私も評価者の立場の時には、このような自己評価を何度かみかけました。本人は努力したつもりでも、評価者の求めているレベルや期待値を理解していないケースです。Bさんと比較しても、高く評価されることはまずないでしょう。
Bさんは、評価者に事前に期待値を確認し、何をすべきか明確にした上で取り組んでいます。評価者からしてみれば、目標とそれに対しての具体的なアクションがあった方が、より適正な評価を下しやすいですよね。正しい評価を勝ち取るためには、事前準備が必要不可欠なのです。
- STEP1 定性評価の期待値を理解する!
- STEP2 目標設定をし、合意を得る!
- STEP3 査定時の自己評価で優位にアピール!
まとめ
今回の記事では、定量評価と定性評価の違いを理解し、適正な評価を勝ち取るための対策をご紹介しました。
- 定量評価と定性評価の違い・特徴
- SMART目標設定の方法
- 定量評価と定性評価への対策と準備
記事中でご紹介したポイントは下記です。
- 定量評価とは、数値で計測できる指標を元にした評価
- 定性評価とは、数値では表すことのできないものに対する評価
- Specific(具体的に):具体的な表現で書かれている
- Measurable(測定可能な):達成率を測ることができる
- Achievable(達成可能な):現実的に達成可能であると同時に挑戦的である
- Related(経営目標に関連した):会社や部署の目標実現に寄与するものである
- Time-bound(時間制約がある):期日が設けられている
- STEP1 明確な目標設定を行う!
- STEP2 現実的なアクションプランをたて、合意を得る!
- STEP3 進捗管理と軌道修正!
- STEP1 定性評価の期待値を理解する!
- STEP2 目標設定をし、合意を得る!
- STEP3 査定時の自己評価で優位にアピール!
自己評価と会社からの評価が一致しない場合、納得いかないこともあるかと思います。もちろん実力不足であったり、自分を過大/過小評価している可能性もありますが、評価のギャップを生まないためには、まず期待値のギャップを埋めることです。
自己満足で自己評価をせずに、評価者の立場に立って日頃から準備をしておきたいですね。

「自分の価値は自分で説明する責任がある。」と指導してくれた上司がいて、本当にラッキーだった。何事も自己責任と思って、準備が大切だね。
以上、ぼしおでした。
本記事を最後までお読みいただきありがとうございます。